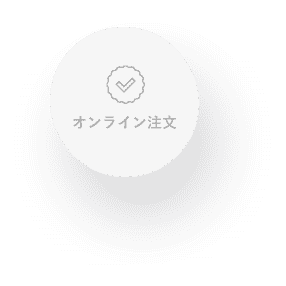食卓を包む色とりどりの笑い声。
そんな色彩にあふれた日常が、時間が経ってもそこにあるものだと思っていた。
『じいちゃんが亡くなった』
電話で聞かせれたその言葉が、彩りを奪っていくように感じた。
久しぶりに揃った家族の顔色は鈍く沈んで、重苦しい空気が漂っている。
『もう随分前から悪かったんだって。』
母の口にしたその言葉が、より一層空気を重くした。
家族が顔を合わせなくなって、もうずいぶん長い。
大人になっていくにつれて、次第に自分の人生を生きることに精いっぱいになって。
繰り返す入院にも、慣れがうまれてきた頃だった。
病院で私物を片付けているときに、便箋の束を見つけた。
内容は変哲のない日記のようなものばかりだった。
でもその日記のような文章の終わりには、決まって孫を思う祖父の気持ちがつづられていた。
きっと寂しかったはずなのに、どうしてその時に気づけなかったのか。
もう謝る事さえできない現実に、ただただ打ちのめされた。
【できることならもう一度、食卓を囲みたい】
【できることならもう一度、ドライブに連れてってもらいたい】
自分も免許をとったことだし、帰りは運転だって変われるのに。
いくら後悔しても足りない、病室で声を殺して泣いていた。
涙もとまって落ち着いたころ、母と姉から葬儀会社との打合せに同席してほしいと言われた。
ばかばかしい話だ。
そんな話はとてもじゃないが、断ろうと思った。
『きっと、じいちゃんも喜んでくれるから。』
姉のその言葉に折れて、渋々同席だけすることにした。
打合せが始まってすぐ、やっぱり、ばかばかしい話だと思った。
『旅葬?バスで観光?』
パンフレットをもらってみても、具体的にどんな内容になるのかは、想像がつかなかった。
『普通の葬儀じゃダメなの?』
最初は真っ向から反対した。
こんなの普通じゃない。
『だって、おじいちゃんも家族も揃って出かけることなんて、もうないじゃない。』
腫れた瞼で嗚咽まじりに訴える母の目は、もう何をいっても聞く耳なんてもってないと言わんばかりだ。
そこまでいうなら仕方ないと、これもまた渋々【旅葬】というものを行うことになった。
予定は全部、母と姉が決めていた。
生前にじいちゃんが行きたかった場所、想い出のある土地。
生家や近所の観光スポットを巡り、最後に向かったその先は、意外だが自分にも縁のある場所だった。
四季彩の丘。
記憶にあるうちでは、じいちゃんと最初に二人ででかけた場所だ。
急に小さかった自分を助手席に乗せて、イイところに連れて行ってやるなんて言って。
あの時も季節は秋頃だったか、雨に濡れたコキアの花が夕日に照らされて、
まぶしくて仕方がなかったのを覚えている。
肩車に乗せられて、じいちゃんがばあちゃんにプロポーズした場所なんだと教えてくれた。
『いつかお前にその時がきたら、ここでプロポーズしてみろ。きっとうまく行くぞ。』
まだ小さい自分にそんなことが分かるわけないのに、自慢げに話すじいちゃんの顔をよく覚えている。
『こんなところでプロポーズなんてうまくいかないよ』
冗談半分に返した自分に、じいちゃんはそんなことはないと、また大きく笑って、
『答えはコキアの花言葉にあるんだ。』
そういって教えてくれたコキアの花言葉。
【恵まれた生活】
じいちゃんの口癖だった。
事あるごとに『こんなに孫に囲まれて、恵まれた生活だ。』なんて大声で笑っていた。
じいちゃんがどんなプロポーズのセリフを口にしたのかはわからないけど、きっとばあちゃんに恵まれた生活を約束したんだろう。
最期の行き先にここを選んだのは、母が見つけた便箋に、いつか家族みんなで見に行きたかったと書いてあったからなんだとか。
全ての行程を終え、帰宅したころには疲れてすぐ寝てしまった。
翌朝、じいちゃんの写真を眺めながら、約束した。
この先、家族の笑い声に彩りを取り戻せるように、恵まれた生活を家族に、と。